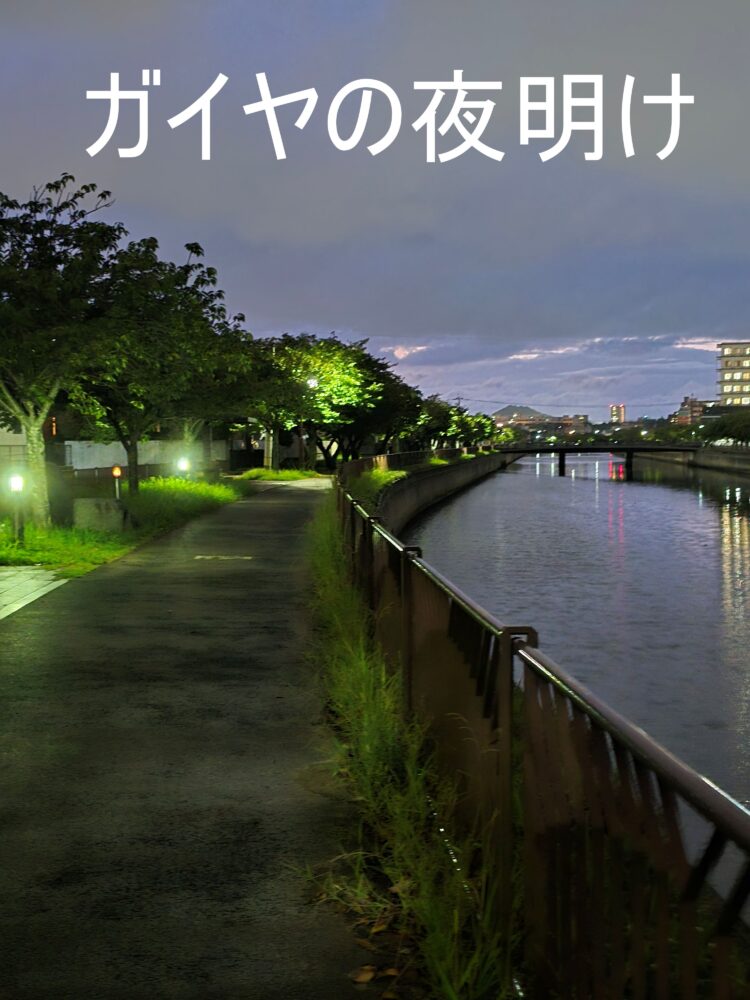この夏も40度を超える酷暑が続き、地球温暖化による気候変動の深刻さを実感させられた。バイオ燃料の利用が広がるのか?国産バイオ燃料の可能性を追った。
「ガイア」とは
ギリシャ神話に登場する「大地の女神」を意味し、後にノーベル賞作家のウィリアム・ゴールディングが「地球」を指して“ガイア”と呼んだことから「ガイア=地球」という解釈が定着している。「ガイアの夜明け」という番組タイトルには、地球規模で経済事象を捉えることで21世紀の新たな日本像を模索すること、そして低迷する経済状況からの再生=「夜明け」を目指す現在の日本を描くという意味合いが込められている。
次世代燃料
この夏も40度を超える酷暑が続き、地球温暖化による気候変動の深刻さを、実感させられた。その温暖化の主な原因とされるのが、化石燃料の使用により排出されるCO2だ。私たちは未来に向かって、CO2の排出量を削減し、温暖化の進行を食い止めることはできるのか?ガイアの夜明けでは2006年に、石油の代替として国産バイオエタノールの事業化に挑む研究者を取材した。
続き①
大手ビール会社に勤めていた小原聡氏だ。当時の番組では小原氏のチームが、エタノールの製造に成功するまで密着した。あれから20年・・・小原氏は既に会社を辞めていた。2016年にバイオエタノールの研究が中止になってしまったのだ。小原氏は大学の研究者としてバイオ燃料の開発プロジェクトを続けていた。
続き②
今回の番組では小原氏が現在、種子島で進めるバイオ燃料のプロジェクトを取材。小原さんはなぜ、困難に直面してもバイオ燃料の事業化を諦めないのか?新たな仲間たちとのプロジェクトを成功させることはできるのか?そのような挑戦で日本でも、バイオ燃料の利用が広がるのか?国産バイオ燃料の可能性を追った。
国産バイオ燃料
国産バイオ燃料は、ソルガムや廃食用油などの非食用バイオマスを原料とし、自動車用エタノールやバイオディーゼル(BDF)など、エンジン車の脱炭素化を目指してトヨタ自動車、ENEOS、マツダなどが国産化に取り組んでいます。農林漁業バイオ燃料法による支援や、カーボンニュートラル移行期の現実的な選択肢として注目されており、給油所の維持やエネルギー自給率向上、経済安全保障の観点からも重要とされています。
開発・生産の現状と背景
- 次世代燃料技術研究組合(raBit)の設立:トヨタ自動車が中心となり、ENEOS、スズキ、SUBARU、ダイハツ、豊田通商、マツダが参加する組合が、イネ科のソルガムなど非食用植物を原料としたバイオエタノールの国産化研究を進めています。
- カーボンニュートラルの移行手段:電動化の移行期間において、既存のエンジン車を低炭素化できるバイオ燃料は現実的な選択肢であり、その国産化が急がれています。
- エネルギー自給率と経済安全保障:現在バイオエタノールの自給率がゼロの日本において、バイオ燃料の国産化はエネルギー自給率向上に繋がり、資源流出の抑制や経済安全保障の観点からも重要です。
- インフラ維持の目的:給油所網の維持はガソリン車の脱炭素化に不可欠であり、バイオ燃料の普及は給油所網の維持にも繋がります。
主な取り組みと技術
- バイオエタノール:ソルガムなどの非食用植物の繊維質を原料として製造する「第2世代」のバイオエタノールの研究開発が進んでいます。
- バイオディーゼル燃料(BDF):廃食用油などを原料として製造するバイオディーゼル燃料メーカーが複数存在します。
- 技術開発の方向性:食料との競合を避けつつ、バイオ燃料の生産コスト低減や、バイオマス資源の効率的な調達が課題とされており、ゲノム編集技術の活用なども研究されています。
関連する取り組みと法律
- 農林漁業バイオ燃料法:農林漁業有機物資源を利用したバイオ燃料の安定的かつ効率的な生産への支援措置を講じており、国産バイオ燃料の生産拡大を後押ししています。
- 各社の参画:トヨタ以外にも、ホンダが藻を、マツダがユーグレナのバイオ燃料製造プラントに出資するなど、各社がバイオ燃料分野での研究開発や投資を進めています。
石油の代替としての国産バイオエタノールの導入は、地球温暖化対策とエネルギー安全保障の観点から重要視されており、経済産業省や農林水産省などが製造実証事業や技術開発を進めています。バイオエタノールは、デンプン質や糖質原料(トウモロコシ、サトウキビなど)から発酵・蒸留して製造され、ガソリンに混ぜて自動車燃料として利用できます。食糧問題やコストが課題ですが、木材や稲わらなどの非食用バイオマスを利用する第2世代バイオエタノールの開発も進んでおり、将来的には カーボンニュートラルなエネルギー源として活用されることが期待されています。